ピボットヒンジ調整の方法・やり方・手順や使い方・流れ

ピボットヒンジ調整の方法概要
ドア調整に必要な道具はプラスドライバーです。プラスドライバーを用意したら、ドア枠の内側にあるピボットヒンジ調整を行います。ドアの本体がドア枠の上にあたる場合はドアを下げる必要があります。ドアを下げるためにはドア右下にあるピボットヒンジをドライバーを使って左に回し高さを調整します。左に回すとドアが下に下がるので、ドアを開閉してスムーズに閉まるようになったかを確認してみましょう。ドア本体の下部がドア枠に接触する場合はドアを上げる必要があります。この場合はピボットヒンジを右に回しドアが上に上がるように調整します。
ピボットヒンジ調整の手順・方法01
ドア本体の開き側がドア枠に接触する場合は、ドア本体を閉じた状態でピボットヒンジの上下の左右調整ネジを左側に回して調整を行います。ドアの開き側の隙間が大きくなりすぎているときは、左右調整ネジを右側に回して調整を行いましょう。ドアの左右のたて枠がねじれているときは、上下のピボットヒンジを固定している固定ネジを調整します。3ヶ所ある固定ネジをドアを押さえながら1回転だけまわします。ドアを手で動かしねじれが解消されたら固定ネジ元の位置へと戻します。以上がドアの開閉に問題が生じた時の解決方法と道具の使い方です。ドアの調整は以上の内容を参考にして手順通りに慎重に作業を行いましょう。
ピボットヒンジ調整の手順・方法02
ピボットヒンジ調整は業者に頼まなくても手順とドライバーの使い方さえわかれば自分で調整が可能です。まず、扉がどうのような状態になっているか確認しましょう。ドア本体が上の枠に当たってしまっていたり、下の枠に当たっている場合に、上の枠に当たっている場合は、ドアを下げてやる必要がありますので、ピポットヒンジ調整カバーを外してドライバーで回して観て下さい。少し上下しているのが判ると思います。下枠に当たる場合も同様にドライバーで上下を調整しながら枠に当たらないような調整をして下さい。この調整でも当たる様であれば枠がねじれている場合があります。
ピボットヒンジ調整の手順・方法03
枠がねじれている場合には、ドアの前後を調整していきます。この場合には、ピポットヒンジが本体と枠に取り付けられていることは判ったと思いますので、ドア本体に固定されているネジを緩めてみると調整が出来ます。この時に全てのネジを緩めてしまうと調整が難しくなりますので、固定されているネジは一か所のみを少し緩め、扉の固定ネジを締め付けてドアの固定をします。一度に完全に緩めてしまうと、調整が難しかしくなりますので注意しましょう。この調整の時は必ず扉を持ちながら、枠に収まる様にしましょう。これで、家の中の扉の殆どを自分で調整が可能です。
ピボットヒンジ調整の手順・方法04
ピボットヒンジは、軸吊り丁番とも呼ばれ、扉の上と下に取り付けて、上下軸を支点として開閉するための金具です。使い方によっては、金物があまり見えずにスマートな見た目になるのと、重量ドアに使用しても吊り下がりが少ないのが特徴です。ピボットヒンジの建て付け調整の手順は、左右方向と上下方向に分かれます。まず、左右方向の調整では、ドアを90度まで開け、上枠取り付け金具の4本のねじをゆるめます。室外側方向に2ミリメートル、室内側方向に1ミリメートル、戸先側に1ミリメートル、吊元側に1ミリメートル動きますので、位置を定めて、ねじを締め直します。
ピボットヒンジ調整の手順・方法05
ピボットヒンジ調整で上下の隙間を調整する場合は、ピボットヒンジ下部軸に六画スパナが取り付けられている場合は、それを使って下部軸のナットを回すことで、上に最大3ミリメートルまで動かすことができます。六画スパナの固定ねじをはずしてから使用します。調整が終わったら、六画スパナをまた固定します。このスパナは、かならず元通りに取り付けなくてはなりません。ナットが回転して、開閉時に不具合が生じる可能性があります。スパナがついていないねじの場合は、適合する器具を探さなければなりません。建て付け調整のしやすいピボットヒンジを選ぶようにしましょう。
ピボットヒンジ調整の考察
ドアの開閉がスムーズでないといったことはないでしょうか。そういった場合の解決方法として、ピボットヒンジを調整することがあるようです。今回はそのピボットヒンジ調整方法を紹介しましょう。まずは、構造を知ることからです。ピボットヒンジにはいくつかの調整ポイントがあり、そこのネジによって上下の調整や左右の調整に作用するようです。ドアが上枠や床にあたるようなら上下調整ねじ、開閉時に横枠にぶつかるのなら左右の調整ねじを閉めたり緩めたりしてください。また、前後の場合には、丁番のゆるみなどが原因となっているようです。
ピボットヒンジ調整のまとめ
住宅のドアの開け閉めの要になっているものが、丁番あるいはピボットヒンジ(軸吊り丁番)です。ピボットヒンジは、見た目がスマートで、重量のあるドアにも耐えられるという特徴があります。ピボットヒンジ調整は、前後方向と左右方向、及び上下方向の3通りあります。前後左右の調整は、ドライバーでネジをまわすことでできるのが普通です。一方で、上下方向の調整は、ナットを回して上げ下げする構造になっているものが多いですから、レンチあるいはスパナを使います。工具を使う時に特に注意したいところは、ネジやナットをまわす時、ネジ山などを潰さないようにネジなどにあった工具を使うことです。
ピボットヒンジ調整で使った言葉の意味・使い方
扉の上端と下端に取り付けて上下軸を支点に開閉するための金具であるピボットヒンジ(軸吊り丁番とも言う)を調整することで、扉の高さの微妙な調節などドア本体の建て付け調整が可能となります。このピボットヒンジ調整には、上下調整ねじ、左右調整ねじ、前後調整ねじがあるので、必要な調整ねじを回すことで微妙な調整ができます。ドア本体の上部もしくは下部が枠に当たるような場合は、上下調整ねじで調整します。調整ねじを左に回すか右に回すかで上下に調整可能です。同じように、ドア本体の開き側が枠に当たるような場合は、左右調整ねじで調節し、左右たて枠がねじれている場合は、前後調整ねじで調節することになります。
ピボットヒンジ調整の方法の注意点
ドアのピボットヒンジ調整方法はドアの状態により異なります。 1つ目はドア本体の上部が枠にあたる場合です。この場合にはドア本体を下げた状態で下のピポットヒンジの軸カバーを取り、上下調節ねじを左回りに締めていきます。調節後は軸カバーを取り付けます。 2つ目はドア本体の下部が枠にあたる場合です。この場合はドア本体をあげた状態で下のピポットヒンジの軸カバーを取り、上下調節ねじを右回りに締めていきます。調節後は同じく軸カバーを取り付けます。 その他ドア本体の開き側が枠にあたる場合にはドアを閉じ、上下のピポットヒンジを左に回します。逆に隙間が大きすぎる場合には右に回していきます。
-

-
割合計算の方法・やり方・手順や使い方
エクセルで割合計算を行うには、まずはセルに計算式を入力します。A1セルの数値が全体の数値として、B1セルの数値がA1セル...
-

-
パソコン初期化XPの方法・やり方・手順や使い方
パソコン初期化XPの方法はリカバリを行います。リカバリはリカバリディスクを利用し、リカバリディスクをCDドライブに入れた...
-

-
【冷凍野菜・解凍】方法・手順・使い方、メリットデメリットなど...
野菜の保存方法には2種類あることが認識されており、通常の場合には冷蔵庫で保存をする冷蔵野菜というものが主流となっています...
-

-
五葉松剪定の方法・やり方・手順や使い方
五葉松の剪定方法ですが、時期でいうと5月頃と10~11月頃の大まかに2回行います。 まず5月になると、新芽が出てくるの...
-

-
【カブトムシ飼育】方法・手順・使い方、メリットデメリットなど...
カブトムシ飼育を成功させる方法は、まずはカブトムシについての基本知識を頭に入れておくことが大切です。 たとえば日本産カ...
-

-
イベントの方法・やり方・手順や使い方・流れなどについて
最近、若い世代から中高年の世代の間で行われるようになっているのが婚活イベントへの参加です。昔では考えられなかったものです...
-

-
画面キャプチャの方法・やり方・手順や使い方
それではPCの画面キャプチャの説明をしていきます。PCの画面をキャプチャするには、まず、キーボードの【PrintScre...
-

-
アルミ溶接の方法・やり方・手順や使い方・流れ
アルミニウムのTIG溶接は交流溶接で行います。電極にタングステンを使い、材料から一定の隙間を開けて溶接しなければならず、...
-

-
【ヤフー・プレミアム会員解約】方法・手順・使い方、メリットデ...
オークションでの出品や無料クーポンなどの特典があるヤフープレミアム会員ですが、毎月の支払いも必要なため不要となった場合は...
-
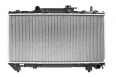
-
ラジエターの交換方法・やり方・手順や使い方
今の自動車に使われているラジエターは、かなり丈夫になっていますからそう簡単には壊れません。ですが消耗品であることには変わ...






ドアの開閉がうまくいかず床を傷付けることもあります。これは、ドアのたてつけがくるっているものです。このゆがみを調整するのがピボットヒンジ調整です。ドア本体が枠に上下部に当たるときピボットヒンジのカバーをはずし上下調整ねじを回して調整します。ドア本体が開き側が枠に当たるとき上下のピボットヒンジのねじをつり元側に調整します。ドア本体が開き側に大きく隙間が開くとき枠側へ調整ねじを調整します。ドア本体がねじれているときピボットヒンジの固定ねじを軽く1回転ゆるめます。次に前後ねじで調整しねじれをとります。最後にゆるめた固定ねじを締めなおします。